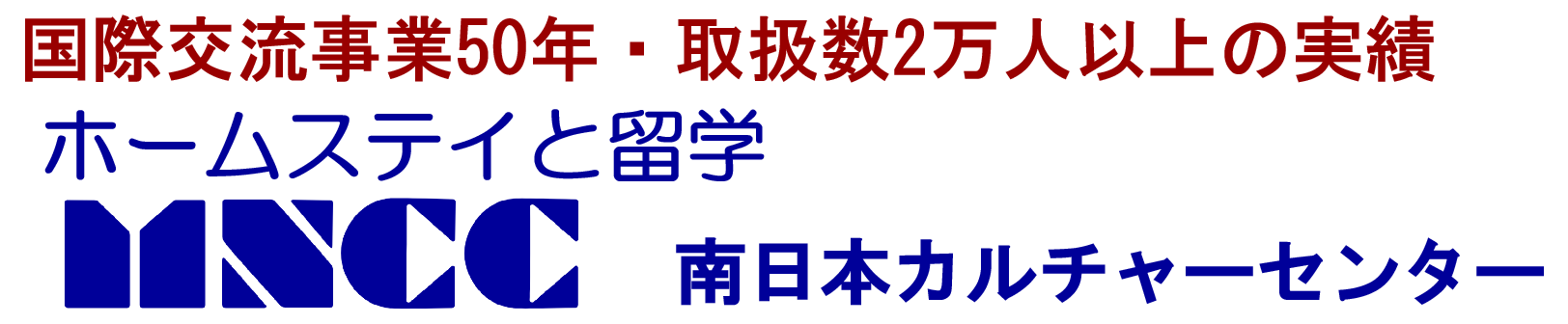
HOME > デミアン君の日本留学顛末記 > 22異文化の狭間で
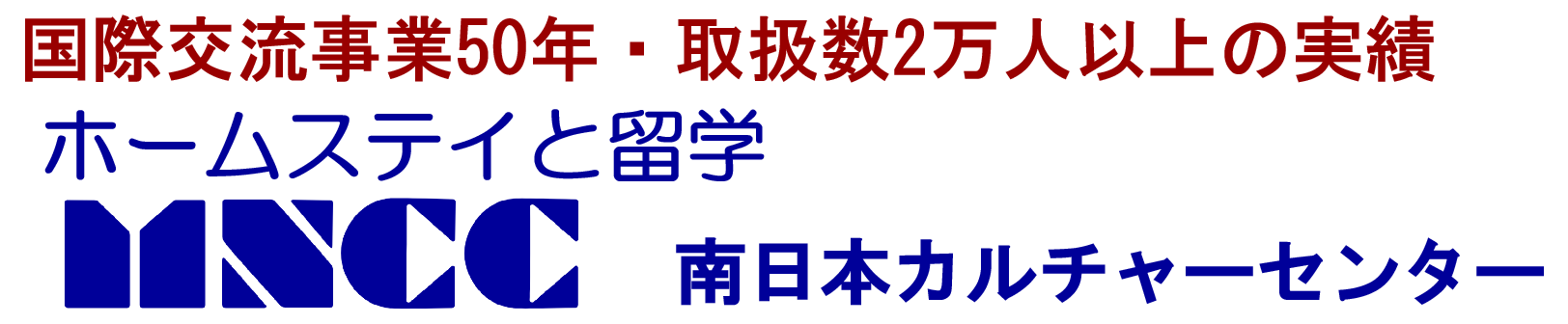
|
15歳の米国人中学生の留学体験記。日本という国で、日本人と生活し、日本文化を体験する彼と、彼と関わりを持つ方々が体験した異文化交流の記録である。そこには多くの日本人が抱く「国際交流」という華やかさはない。
HOME > デミアン君の日本留学顛末記 > 22異文化の狭間で |
|
|
筆 者: 濱 田 純 逸 22.異文化の狭間で結局、4万円弱のデミアン君の修学旅行費用は、桜島町の教育委員会の先生方を始めとする、数多くの方々の協力と善意によって、支払われることとなった。いわば日本流の外国人への温かいもてなし方と、献身的な接し方の文化が、ここでもまた、直接的に大きな現実問題を解決してくれた。でも、この日本の文化による善意の解決方法を、デミアン君がどのように理解したかは知らない。最後の最後まで、この事は聞かなかった。 「何故、日本人はこれほどまで自分のためにしてくれるのだろう」と思ったかもしれない。あるいは、「自分は、この申し出を受け入れることはできない」と思ったかもしれない。また、「この善意は、自分には苦痛を伴う、過ぎた申し出だ」と思ったかもしれない。もしくは、それまでに、度重なる日本人の外人に対する過ぎた親切と、接待の習慣に慣らされていたのであるならば、そのような疑念や自問を抱く前に、「ただただ、感謝するだけだ」と思っただけだったかもしれない。 この度重なる、また時には度の過ぎた日本人による外人への温かいもてなしは、あらゆる戸惑いと驚きと影響を彼らに与えている。来日するホストファミリーを始めとする、米国人と接する機会が仕事上多い。そして、彼らのお世話をしている時に、必ず、彼らに対する日本人の過剰すぎる接遇ぶりを、目の当たりにするのである。一緒に食事に行って、彼らがお金を払ったのを見たことがない。一緒に観光地に行って、彼らが入場料を払うのを見たことがない。彼らがホームステイしている間のホストファミリー宅での朝食や夕食を聞けば、それがいつもの食事ではないことはすぐにわかるのだ。 ある来日した米国人とアメリカで再会した時、居合わせた米国の知人に日本での思い出を「私は、まるで女王様だったの。何もしなくても、すべて面倒見てくれた。」と語った彼女に、大きな違和感を感じたことがある。もちろん屈託なく、自分がいかに厚遇されたかを説明するための表現であり、他意はなかったが、釈然としないものが残った。そして、もう一つ自分が体験した思い出と一緒に、これら2つの物語は私の心深くに封印されているのである。 あれは、1978年5月の連休のことである。会社で新しく雇用したばかりの米国人女性職員と、私の友人、私の3人で、開聞岳の登山に行った。開聞岳の中腹で、登山途中に休憩をした際、彼女の話題は友人がかぶっていた帽子に集中した。当時としては、やや流行遅れのいわゆるチューリップ帽と呼ばれていたものであったと記憶する。その帽子を彼女は、いたく気に入ったらしく、いい帽子だと褒め称えたが、私には何の変哲も無いありきたりのものでしかなかった。その後、登頂して私の運転する車で、鹿児島へ向う途中、友人は谷山市街地で下車した。その時、彼は、今までかぶっていた帽子を彼女に差し出し、今日の想い出にというようなことを言って、立ち去ろうとした。あっという間の出来事であったが、渋滞の妨げにならないようにとの思いで、彼女が彼を呼び止め、帽子を返そうとしているのを制止して、私は車をそのまま発進させた。私自身、彼のとった行為に何の不自然さも感じなかったし、日本人に散見される、外国人に対する典型的な接し方の一つであり、それまでは、私には何の違和感もなかった。 ところが、二人っきりになった車の中で、彼女は私に、「先ほど、自分がこの帽子のことをほめたのがいけなかったのか」と、訳の分からぬことを聞いてきた。その表情は明らかに動揺し、困惑しているようであった。要領を得ない彼女の質問に、いろいろ受け答えしているうちに、ようやく彼女の話の真意と、その背景が理解されてきた。 日本に来る前に、日本のことについて本を読んだり、調べたり、在日体験のある米国人から聞いたりした中で、「もし、あなたが日本で、日本人の持っているものを欲しかったら、その品物を褒めればいい。そうすれば、あなたは手にする事ができるだろう。」というようなことを知らされたというのだ。彼女としてみれば、当然、日本に来て日が浅く、そんなことすら忘れていた中で、純粋にその帽子を褒めたところ、その情報通りの顛末になったので、かなり当惑したというのである。そして、自分は欲しくてそうしたのではないと自己弁解する。彼女のその驚きと戸惑いが忘れられない。でも、そのような内容のことが、米国社会の中で日本と日本人に関する情報の一つとして、私達の知らないところで、喧伝され、流布しているのかと思えば、はなはだ、不愉快な感情を持ったことだけは覚えている。その後、数多くのALTやCIRの方々と会うたびに、彼らもあの情報を得た上で、日本にやってきているのかと考えれば、純粋に、平然とした気持ちで接することはできず、やりきれない気持ちでいっぱいであった。 文化の差といえば一言かもしれないが、その背景には、彼らとの出会いを一過性の出来事としてとらえられるからこそ、その献身的もてなしと厚遇が、可能になっているのではないのか。そして、それはまだまだ、九州の我々の周囲には多くの外人達がいないからこそ、できていることなのかもしれない。決して私は、この日本人の外人に対するもてなしの仕方を否定しようとは思わない。親身になってもてなす、お客様への繊細な気配りと親切は、日本人の伝統的な美徳の一つと思う時もある。でも、外国人労働者問題や経済難民の増加、さらには、8千人を超すALT、CIRの雇用による教育現場での文化摩擦、また、経済の発展と共に、好むと好まざるとに関わらず押し寄せるボーダーレス社会など、周囲にある益々国際化して行く日本の環境と、予測できる将来を思うに、この日本流のもてなし方の慣習と接し方を、いつまで持ち続けることができるのだろうと考えざるをえない。そうすると、大きな大きな自己矛盾を感じ、不安を思うのである。そして、これらの外国人に対する過剰と思えるほどの、日本人のもてなし方が見られなくなったとき、また、外人という言葉が死語になり、内と外の区別を観念的に、意図的に、考えなくなったとき、日本に初めて、国際化における本当の問題が発生するときだと思うのである。そういう意味では、現在の日本における外国人と日本人の文化摩擦問題は、極めて特殊なものであり、普遍的な文化摩擦の問題だという認識はない。単一民族であり、島国であり、隣接する国境がない地理的環境に起因する独特の問題である。 考えてみれば、数多くのALTやCIRが、地方自治体によって招聘されて久しい。また、「留学生10万人計画」の政策によって、これまで来日した留学生の数も膨大だ。さらには、不法外国人労働者の数は30万人近いというデータもある。これらの外国人が、長期にわたって、地域に滞在している。学校現場では同僚や教師や学生として、役場や市役所の地方自治体でも同僚や指導者として、職場では同僚や被雇用者として、そして、彼らの生活場所では住民として、数多くの日本人と接触が起きている。その接触に、我々日本人はどう反応しているのだろうか。果たしてその接触から、数多くの日本人達は、何を学んでいるのだろうか。そんなことを考えれば、指導者のいない、安穏とした異文化の接点があるだけでは、何も進まず、問題の深さだけが露呈され、遅々とした異文化理解の現実を見るにつれ、慄然としてしまうのである。
|
| MNCC 南日本カルチャーセンター Copyright © 2007 MinamiNihon Culture Center. All Rights Reserved. http://www.mncc.jp |