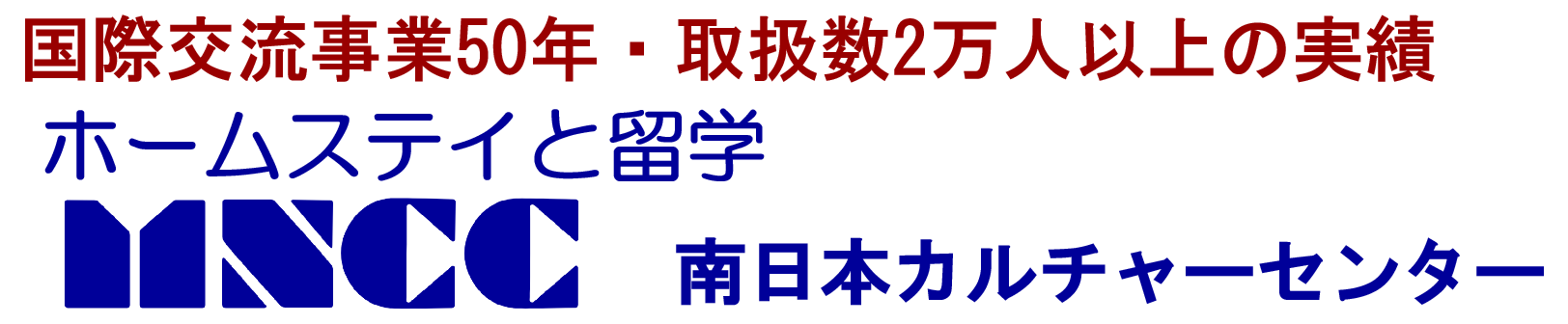
アカデミックホームステイに参加したある中学生のホームステイ記録(日記)です。彼女がホームステイの中で、何を感じ、何を思い、何を考え、何を得たのか。
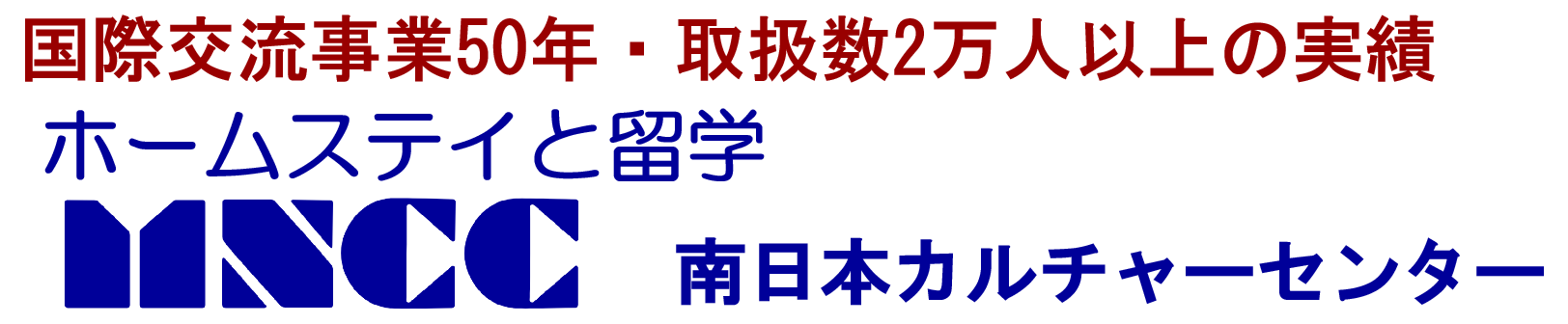
|
アカデミックホームステイに参加したある中学生のホームステイ記録(日記)です。彼女がホームステイの中で、何を感じ、何を思い、何を考え、何を得たのか。
|
|
|
筆 者: 濱 田 純 逸 ●08月21日 木曜アメリカでの生活もあと一週間。さよならパーティー【注094】の話がでるようになった。女子のたまり場のトイレで何をするか計画中。みんなこのごろまとまった【注095】みたい。すごく話がはずむ。男子は隣の部屋。外人の子がびっくりして目を白黒させていた。歌を選ぶのに意見が分かれる。私は日本的な歌がいいと思うのだけど。民謡とか。パーティーのときはきものらしい。どうしよう、ゲタがない。安いのを買うかな、ジャパニーズストアで。明日は疲れるだろうなあ。一日中というか、何時間もバスにゆられて湖へ行って泳いで、そして帰ったらこんどはショッピング。でも楽しいことばっかりの疲れだからすぐ元気になるだろう、私のことだから。今日もおなかがいっぱいで死にそう。夕方こっそり(ラナ、キムのダンスの練習日)冷蔵庫から【注096】パンをとりだしたり、バナナを食べたり、チョコ入りのクッキーを食べたりしたからな。夕食もなぜかごうかだったし。このごろしあわせ……【注097】。すきやきの作り方、思い出すのにいっしょうけんめい。えっとはじめに肉をいためて、かたいのを入れて、それからしょうゆとさとうを適当に入れて・・・。うーっ、本当に大丈夫かな。一回も作ったことないのに。がんばろう。
|
|||||||||||||||||||||
| MNCC 南日本カルチャーセンター Copyright © 2007 MinamiNihon Culture Center. All Rights Reserved. http://www.mncc.jp |